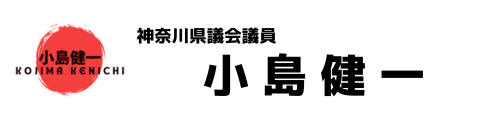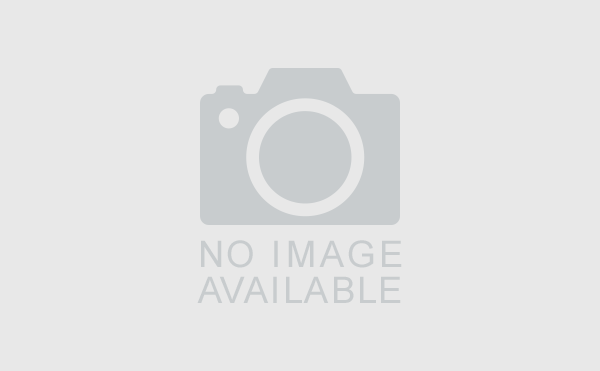NO.224 備蓄米と日本の農業
6月に入り、小泉農相肝いりの備蓄米が全国で流通し始めた。何よりもスピード感が大事ということで、それまでの競争入札ではなく随意契約で政府が民間に売り渡した備蓄米は5キロ2000円程度で緊急販売されている。その意図するところは、高止まりしている5キロ4000円代の米価を下げるためだが、減反政策の問題を含め、様々な意見が続出している。
私自身は、国家財産である備蓄米について、財務省がよく随意契約で売却することを認めたなというのが第一印象だ。さらに、国民民主党の玉木代表が「備蓄米は一年経ったら動物の餌になる」と国会で述べて批判を浴びたが、実際、古古古米は加工食品、家畜の餌等に使用されるのは事実である。さらに言えば、そういった古い米は受刑者や自衛隊員がこれまで食べてきたのも隠れた事実なのだ。
また、小泉農相は米価が下がらない原因に関して、J Aや卸業者に言及しているが、そもそもの原因は日本が減反政策をずっと続けてきたことにあるのではないか。減反政策は一応2018年に終了したことにはなっているが、その後も政府は需要をギリギリ満たす程度に生産を減らしてきたのだ。
日本の食料自給率はカロリーベースで38%と先進国で一番低い。食料安全保障の観点からも、米国と同様に、小売価格と生産コストの差額について政府が全面的に農家を補填するような政策をとるべきだ。こんな米不足の中、輸出を8倍に増やすと政府が基本計画に書いているのなら尚更のことである。
小泉農相は、備蓄米が尽きた場合、外国産米の緊急輸入も検討すると述べた。しかし、安易な輸入米促進は結果的に国内農業を疲弊させるだけではないか。そして、今後、農業の大規模化やスマート化を推進する方針が示されているが、それによって国防としての農業が本当に守られるのか。
日本中の田んぼに醜い中国製の太陽光パネルが張り巡らされている。脱炭素というまやかしから目覚め、美しい田んぼを復活させるべきだ。